ここ数年、暦年贈与課税について税制改正する検討が進められています。最近は雑誌の記事やニュース等でも「相続税と贈与税の一本化」に関しての記事をよく見かけるようになりました。今回は生前贈与と相続税の税負担に関して解説したいと思います。
ページコンテンツ
(1)暦年贈与課税の仕組み
贈与税は1月1日から12月31日までの期間を課税の単位とし、その期間に贈与を受けた財産の合計額を算出し、財産をもらった人(受贈者)に対して課税されます。
年間110万円までは基礎控除額があり、もらった財産が年間110万円を超えた部分が課税対象となります。
なお、扶養義務者間の生活費や養育費などは贈与税の対象外となるため、それらの財産に関しては贈与税の計算から除外されます(参考:国税庁「贈与税がかからない場合」)。
贈与税はもらった財産が多ければ多いほど適用される税率が高くなり(超過累進税率)、税負担が重くなります。ただし、受贈者によって適用される税率が異なっており、①直系尊属(父母、祖父母など)から20歳以上の直系卑属(子、孫など)に対して行われる贈与と、②それ以外の人へ行われる贈与では適用される税率が異なります。
①の場合は「特例贈与」に該当し、②の場合は「一般贈与」に該当します。具体的な税率は下記のとおりです(参考:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)。
【贈与税の速算表】

【贈与税額の算出イメージ】
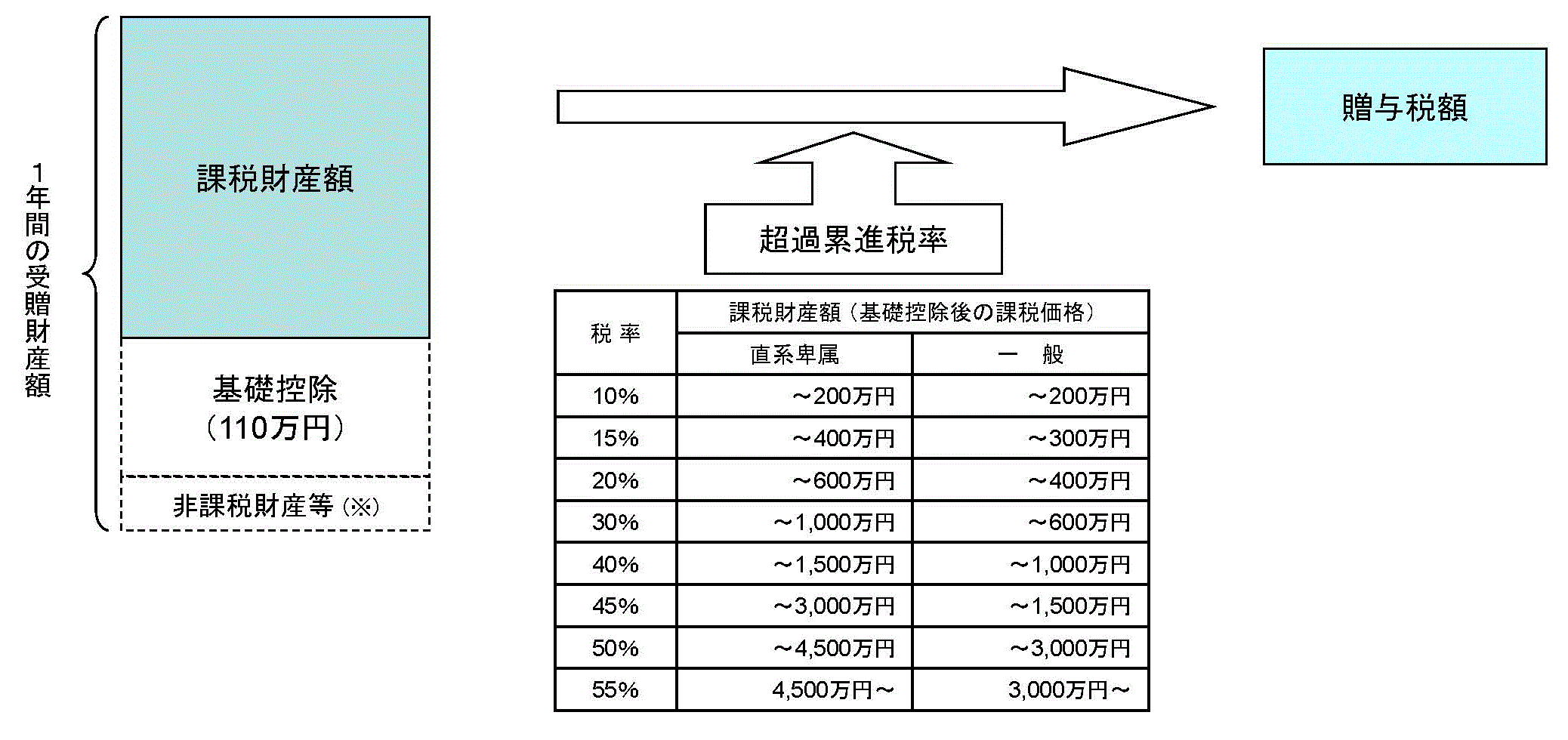
(出典:財務省「贈与税に関する資料」)
(2)相続税の限界税率と生前贈与の活用
贈与税は1年間に贈与された金額で税負担が決まってきますが、相続税は相続発生日における財産額によって税負担が決まってきます。相続税も贈与税と同様に超過累進税率となっており、税率は下記の表のとおりです。
【相続税の速算表】

※「法定相続分に応じた取得財産」は基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を控除し、法定相続分で按分した金額
例えば、相続財産が2億円、相続人が子供1人の場合、速算表にあてはめると相続税額は下記のとおりとなります。
①相続財産2億円-基礎控除額3,600万円=1億6,400万円
②1億6,400万円×40%-1,700万円=4,860万円
この場合の税率40%のことを「限界税率」といいます。本来の計算では、「1,000万円以下の部分は税率10%、1,000万円〜3,000万円の部分は15%・・・」というように金額に応じた税率で計算し、その結果を合計して相続税を計算することになります。
しかし、この方法だと計算が煩雑になるため、速算表により取得財産額に応じた最高税率をかけて、その後、税率の低い部分を控除する方法で計算します。 つまり、表面的には取得財産額に40%の税率がかかっているように見えますが、低税率部分の1,700万円を控除しているため、実際に40%の限界税率が適用されているのは1億円を超えた部分だけになります。
(参考ですが、実際の相続税4,860万円を相続財産2億円で割って算定した24.3%のことを「実効税率」といいます。「限界税率」や「実効税率」は贈与税などの他の租税でも考え方は同じです。)
もし、上記の設例のような方がいる場合、「相続が発生したら1億円を超える部分の遺産については40%の税率で相続税がかかるのならば、自分が生きているうちに40%よりも低い税率で生前贈与をしておこう・・」と考えるのはある意味では自然とも考えられます。
実際に生前贈与を行う際に問題になってくるのが「いくらを贈与するか」ということですが、ここで出てくるのが「限界税率」の考え方です。つまり、相続税の「限界税率」よりも低い贈与税の「実効税率」で生前贈与を行っておけば、その税率の差額分、節税になるということになります。
例えば、上記の設例の場合で、自分の子供に1,000万円の「特例贈与」を行った場合の税負担は下記のとおりです。
①贈与税の負担
1,000万円-110万円=890万円
890万円×30%-90万円=177万円 ※贈与税の実効税率=177万円÷1,000万円=17.7%
②相続税の負担
相続財産2億円-生前贈与1,000万円=1億9千万円
相続財産1億9千万円-基礎控除額3,600万円=1億5,400万円
1億5,400万円 ×40%-1,700万円=4,460万円
③ ①+②=4,637万円
贈与税を負担してでも生前贈与を行った場合、トータルの税負担は223万円少なくなりました。相続人が複数いる場合や相続人以外(子の配偶者や孫など)への贈与、または複数年に分けて少額の贈与を行う場合は、トータルの税負担をさらに抑えることが可能です。
(3)贈与を行う際の注意点
自分が高齢になってきたら財産を子供などに贈与しておいて、相続財産を減らしておこうと考えることは多いと思います。
しかし、生前贈与を行った場合には、「相続等により財産を取得した人がその相続開始前3年以内に暦年贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算する」という内容の規定があるため注意が必要です(いわゆる「生前贈与加算」と呼ばれるものです)。この規定により、相続発生直前に贈与を行い相続財産を減らしておこうという考えは封じられています。
3年より前の生前贈与に関しては加算の対象となりませんが、「そもそも贈与が成立していない場合」には、仮に被相続人名義の財産ではなくても、相続税を計算するうえでは「被相続人の本来財産」(名義預金)として認定されるため注意が必要です。
「贈与が成立している」と言うためには、財産をあげる側の意思と財産をもらう側の意思が合致していることが必要です。つまり、「贈与者」と「受贈者」の両方の意思が無いと贈与は成立しないこととなります。
例えば、子供に内緒で子供名義の通帳に預金を預け入れている場合は子供側で「財産をもらった」という意思が無いため贈与は不成立となります。また、意思能力がない認知症の親の口座から預金を下ろしている場合には親側で「財産をあげた」という意思が無いため贈与は不成立となります。
(4)今後予想される改正
相続税と贈与税の一体化に関して、令和3年度税制改正大綱の中で今後の検討事項として下記のように記載があります。
「高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による資産の世代間移転の時期がより高齢期にシフトしており、結果として若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた、経済の活性化が期待される。このため、資産の再分配機能の確保に留意しつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築することが重要な課題となっている。 わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず、税負担が一定となり、同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている。 今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」 「令和3年度税制改正大綱より」
主要国(米・仏・独)では、贈与税・遺産税(相続税)の税率が共通で、相続・贈与に係る税負担の中立性が保たれています(参考:「第4回税制調査会(2020年11月13日)説明資料」)。また、マイナンバーや電子申告の普及により、過去の贈与の情報が容易に把握できるようになってきています。それらを考慮すると、今後の改正としては下記のようなことが考えられます。
①暦年贈与課税を廃止し、相続時精算課税制度に一本化する。
②生前贈与加算の期間を3年間より長期にする。
③相続人以外の者(例えば2親等の親族等)への贈与も生前贈与加算の対象とする。
※相続税と贈与税の一体化に関して令和4年度税制改正大綱では改正点は見受けられなかったため、令和4年も以前と同様の税制となりました。
(5)まとめ
相続税率と贈与税率の違い、また税率の違いを活用し生前贈与することでトータルの税負担を抑えることができることを解説しました。相続税と贈与税に関しては今後改正されることが予想されますが、遡って適用されることは基本的には無いため、改正される前に贈与することも検討する必要があるかもしれません。本格的に対策を行う場合には現状の相続税率を把握する必要があるため、まずはご自身の財産額を把握する所から始めてみるのもいいかもしれません。




